| 1B |
�J���ҍЊQ�⏞�ی��@�@��b�m���Ɖߋ����@Tome�mHome�� |
| �@�N���̎x�����@�A���x���̕ی����t |
| �֘A�@�N���̎x�����@(9��)�A���x���̕ی����t(11��)�A���x���̕ی����t�ɂ���(�ʒB(S41.01.31�73) |
�֘A�ߋ���@12-6B�A15-2A�A15-2B�A15-2C�A15-2D�A15-2E�A19-3A�A19-3B�A19-3C�A19-3D,�A22-5A,B,C,D,E�A24-4E�A27-7�A�A30-4�A�A30-4�C�A30-4�E�A�ߌ��1A�A��2-2E,
��3-2�I���A��6-2�I�� |
�N
��
��
�x
��
��
�@ |
1�D�N���̎x�����@(9��)
�@��N������ی����t�̎x���́A�x�����ׂ����R�����������̗�������n�߁A�x�����錠�������ł������ŏI�����̂Ƃ���
�˂��Ƃ��A���a(�⏞)�N���́A����ɐ�ւ�������̑����錎�̗�������x������A���a�����ɊY�����Ȃ��Ȃ�����(�x���v���ɊY�������������ł�����)�̑����錎�܂Ŏx�������B
�@�2���@�N������ی����t�́A���̎x�����~���ׂ����R���������Ƃ��́A���̎��R�����������̗������炻�̎��R�����ł������܂ł̊Ԃ́A�x�����Ȃ��
�˂��Ƃ��A�⑰�⏞�N���́A���̎��҂�1�N�ȏ㏊�ݕs���̂��߁A�����ʎҁA���Ȃ��Ƃ��͎����ʎ҂��\�������Ƃ��́A���ݕs���ɂȂ������̑����錎�ɗ�������A���̎҂ւ̎x���͒�~�����B
�@���ݕs���҂�����Ďx����~�����̐\���������ꍇ�́A���̓��̑����錎�̗�������A���̎��҂̂ւ̎x�����ĊJ�����B
�@�3���@�N������ی����t�́A���N2���A4���A6���A8���A10���y��12����6���ɁA���ꂼ�ꂻ�̑O�����܂ł��x�����B
�@�������A�x�����錠�������ł����ꍇ�ɂ����邻�̊��̔N������ی����t�́A�x�������łȂ����ł��Ă��A�x�������̂Ƃ���
�˂��Ƃ��A6��1���Ɏ������������ꍇ�́A�N���̎x����7��������͂��܂�A�ʏ�̏ꍇ�A7������8���Ɏx������B
�@�Â��āA8������9������10���ɁA�ȉ��A2���������������Ɏx������B
�@12��1���Ɏ������ł����Ƃ��́A12�����܂Ŏx�������B�ʏ�̏ꍇ�A12�����͗�2���x�����ł��邪�A�Ŋ��̏ꍇ�͂����Ԃɍ����Η�1���Ɏx������B |
19
3A |
�@�N������ی����t�̎x���́A�x�����ׂ����R�����������̗�������J�n����A�x�����錠�������ł������ŏI������B(��b) |
|
��������� |
|
27
7� |
�@�N������ی����t�̎x���́A�x�����ׂ����R��������������n�߂��A�x�����錠�������ł������ŏI������B(19-3A�̗ތ^) |
|
��������� |
|
�ߌ�
1A |
�@�N������ی����t�̎x���́A�x�����ׂ����R�����������̗�������n�߂���̂Ƃ���Ă���B(19-3A�̗ތ^) |
|
��������� |
|
19
3B |
�@�N������ی����t�́A���̎x�����~���ׂ����R���������Ƃ��́A���̎��R�����������̗������炻�̎��R�����ł������܂ł̊Ԃ́A�x������Ȃ��B(��b) |
|
����������@�@
|
|
24
4E |
�@�N������ی����t�́A���̎x�����~���ׂ����R���������Ƃ��́A���̎��R�����������̗������炻�̎��R�����ł������܂ł̊Ԃ́A�x�����Ȃ��B(19-3B�̗ތ^) |
|
��������� |
|
��
3
2
�I
�� |
�@�N������ی����t�́A���̎x�����~���ׂ����R���������Ƃ��́A|
C�@|�̊Ԃ́A�x������Ȃ��B |
|
�E��������� |
��Q�͂����� |
19
3C |
�@�N������ی����t�́A���N2���A4���A6���A8���A10���y��12����6���ɕ����āA���ꂼ�ꂻ�̑O�����܂ł��x�����邱�ƂƂ���Ă���A���̎x�����錠�������ł����ꍇ�́A���̏��ł������ɉ������L�̎x���������͂��̎x������ׂ��҂��w�肵�����Ɏx������B |
|
��������� |
|
|
��
�@
�@
�x
�@
�@
��
�@
�@
��
�@
�@
��
�@
�@
��
�@
�@
��
�@
�@
�t |
2�D���x���̕ی����t(11��)
�@����̖@���Ɋ�Â��ی����t���錠����L����҂����S�����ꍇ�ɂ����āA���̎��S�����҂Ɏx�����ׂ��ی����t�ł܂����̎҂Ɏx�����Ȃ��������̂�����Ƃ��́A���̎҂̔z���(�����̓͏o�����Ă��Ȃ����A�����㍥���W�Ɠ��l�̎���ɂ������҂��܂ށB�ȉ�����)�A�q�A����A���A�c���ꖔ�͌Z��o���ł����āA���̎҂̎��S�̓������̎҂����v�������Ă��������A(�⑰(�⏞)�N���ɂ��Ă͓��Y�⑰(�⏞)�N�����邱�Ƃ��ł��鑼�̈⑰)�́A
�@���Ȃ̖��ŁA���̖��x���̕ی����t�̎x���𐿋����邱�Ƃ��ł���
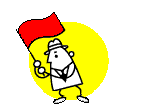
�@���x���̋��t(�܂����̎҂Ɏx������Ă��Ȃ����t)�Ƃ́A
�E���t�𐿋����A�x�����肪���������A�܂��x������Ă��Ȃ����̂����邤���Ɏ��S
�E���t�𐿋��������A�܂��x�����肪�Ȃ������Ɏ��S
�E�܂��������Ă��Ȃ������Ɏ��S
�˂�������A���S�����܂łɂ��Ė��x���̕���������A�����̖��O�Ő����ł���B
�@�2���@�O���̏ꍇ�ɂ����āA���S�����҂����S�O�ɂ��̕ی����t�𐿋����Ă��Ȃ������Ƃ��́A�����ɋK�肷��҂́A���Ȃ̖��ŁA���̕ی����t�𐿋����邱�Ƃ��ł���
�˖{���̎��҂��܂��������Ă��Ȃ������Ɏ��S�����ꍇ�ł��A���Ȃ̖��O(���x���̋��t�̐����҂̖��O)�Ő����ł���B
�@�3���@���x���̕ی����t����ׂ��҂̏��ʂ́A1���ɋK�肷�鏇���@(�⑰(�⏞)�N���ɂ��ẮA16����2��3��)�ɋK�肷�鏇��)
�ɂ��
�ˈ⑰(�⏞)�N���ɂ��ẮA ���S���҂Ɠ����ʎ҂�����Ƃ��͂��̎ҁA���Ȃ��Ƃ��͎����ʎ�(�]��������)�x������B
�@�����ŁA�D�揇�ʂ�16����2�ɂ���悤�ɁA��z��ҁA�q�A����A���A�c���ꖔ�͌Z��o���̏��ł��邪�A���v�ێ������A�N��v���A��Q�v�������Ă���(���Ȃ킿�A�⑰(�⏞)�N�����邱�Ƃ��ł����)�̗D�揇�ʣ�ł���̂ŁA���̖��x�����t�Ƃ͈قȂ�B
�@�4���@���x���̕ی����t����ׂ������ʎ҂���l�ȏ゠��Ƃ��́A���̈�l�����������́A�S���̂��߂��̑S�z�ɂ��������̂Ƃ݂Ȃ��A���̈�l�ɑ��Ă����x���́A�S���ɑ��Ă������̂Ƃ݂Ȃ���@
�@���x���̕ی����t�ɂ���(�ʒB(S41.01.31�73)
�@����x���̕ی����t�ɂ��ẮA�]���͈⑰(�⏞)���t�ȊO�͂��ׂĎ��҂̑����l�Ɏx�����邱�ƂƂ��Ă������A�N������ی����t�ɂ��ẮA���҂����S�����ꍇ�ɂ͕K�����x������������̂ŁA�ی����t�̑啝�N�������@��ɁA
�@���x���̕ی����t�ɂ��ẮA���̎������p����ɂӂ��킵�����Ƃ��āA���҂Ɛ��v�������Ă����⑰�B
�@���x�����̈⑰(�⏞)�N����
���ẮA�����ʂ̎��ҁA�����ʂ̎��҂����Ȃ��Ƃ��͎����ʂ̎���(���Ȃ킿�]�������)�𐿋����҂Ƃ����
 ���x���̕ی����t�̋K��͊e�@�قڋ��ʂł��邪�A�J�Еی��@���L�Ȏ����́A ���x���̕ی����t�̋K��͊e�@�قڋ��ʂł��邪�A�J�Еی��@���L�Ȏ����́A
�P�D�⑰(�⏞)�N���Ƃ��̑��̕ی����t(�⑰(�⏞)�ꎞ�����܂�)�Ƃł́A��舵�����قȂ�B
�Q�D�⑰(�⏞)�N���̏ꍇ�́A�]�����x������̂ŁA
�@�@���S�������҂Ɠ���D�揇�ʎ�(�ꏏ�Ɏ��Ă�����)������ꍇ�́A���̎҂���������B
�@�A���Ȃ��ꍇ�́A���̏��ʂ̎�(�]���ɂ��⑰(�⏞)�N�����ł����)����������B
�R�D���̑��̕ی����t�ɂ��ẮA
�@���v�����́A�z���(���������܂�)�A�q�A����A���A�c���ꖔ�͌Z��o���̏��ōŏ�ʎ҂���������B(�e�@�Ƌ��ʂł���)
�S�D�J�Еی��@�ɂ����ẮA���x���̋��t����҂����Ȃ��ꍇ�������l������𐿋��ł���B
�ˌ��N�ی��@�ɂ����ẮA���x���̋��t���̂��̂��K�肪�Ȃ��̂ŁA�����l����������B
�ˑ��̏ꍇ�́A�����l�͐����ł��Ȃ��B |
��
6
2
�I�� |
�@�N������ی����t�̎x���́A�x�����ׂ����R��������|
C�@|����n�߁A�x�����錠�������ł������ŏI�����̂Ƃ���B�܂��A�ی����t���錠����L����҂����S�����ꍇ�ɂ����āA���̎��S�����҂Ɏx�����ׂ��ی����t�ł܂����̎҂Ɏx�����Ȃ��������̂�����Ƃ��́A���̎҂̔z��ҁA�q�A����A���A�c���ꖔ�͌Z��o���ł����āA���̎҂̎��S�̓������̎҂Ɛ��v�������Ă������̂́A|
D�@|�̖��ŁA���̖��x���̕ی����t�̎x���𐿋����邱�Ƃ��ł���B(��b) |
|
�E��������� |
��Q�͂����� |
12
6B |
�@�ی����t�̎��҂����S�����ꍇ�ɂ����āA���̎҂Ɏx�����ׂ��ی����t�ł܂��x������Ă��Ȃ��������̂�����Ƃ��́A����̈⑰�́A���Ȃ̖��ɂ����Ė��x���̕ی����t�̎x���𐿋����邱�Ƃ��ł���B(��b) |
|
��������� |
|
15
2A |
�@�ی����t���錠����L����҂����S�����ꍇ�ɂ����āA���̎��S�����҂Ɏx�����ׂ��ی����t(�⑰�⏞���t�y�ш⑰���t�Ɋւ�����̂�����)�ł܂����̎҂Ɏx�����Ȃ��������̂�����Ƃ��́A���̎҂̔z���(�����̓͏o�����Ă��Ȃ����A�����㍥���W�Ɠ��l�̎���ɂ������҂��܂�)�A�q�A����A���A�c���ꖔ�͌Z��o���ł����āA���̎҂̎��S�̓������̎҂Ɛ��v�������Ă����҂́A���Ȃ̖��ŁA���̖��x���̕ی����t�̎x���𐿋����邱�Ƃ��ł���B(��b) |
|
��������� |
|
��
2
2E |
�@�J�Еی��@�Ɋ�Â��ی����t���錠����L����҂����S�����ꍇ�ɂ����āA���̎��S�����҂Ɏx�����ׂ��ی����t�ł܂����̎҂Ɏx�����Ȃ��������̂�����Ƃ��́A���̎҂̔z���(
�����̓͏o�����Ă��Ȃ����A�����㍥���W�Ɠ��l�̎���ɂ������҂��܂ށB)
�A�q�A����A���A�c���ꖔ�͌Z��o���ł����āA���̎҂̎��S�̓������̎҂Ɛ��v�������Ă�������(
�⑰�⏞�N���ɂ��Ă͓��Y�⑰�⏞�N�����邱�Ƃ��ł��鑼�̈⑰�A�⑰�N���ɂ��Ă͓��Y�⑰�N�����邱�Ƃ��ł��鑼�̈⑰)
�́A���Ȃ̖��ŁA���̖��x���̕ی����t�̎x���𐿋����邱�Ƃ��ł���B |
|
��������� |
|
��
�x
��
��
��
�t
�E
�D
��
��
�� |
15
2B |
�@���x���̕ی����t(�⑰�⏞���t�y�ш⑰���t�Ɋւ�����̂�����)����ׂ��҂̏��ʂ́A�z��ҁA�q�A����A���A�c����y�ьZ��o���̏����ɂ��B(15-2A�̉��p) |
|
��������� |
|
22
5
A
B
C
D
E |
�@�J�Еی��@�Ɋ�Â��ی����t���錠����L����҂����S�����ꍇ�ɂ����āA���̎҂Ɏx�����Ȃ��������̂�����Ƃ��́A���̎҂̔z���(�����̓͏o�����Ă��Ȃ����A�����㍥���W�Ɠ��l�̎���ɂ������҂��܂�)���ł����āA���̎҂̎��S�̓������̎҂Ɛ��v�������Ă�������
�́A���Ȃ̖��ŁA���̖��x���̕ی����t�̎x���𐿋����邱�Ƃ��ł��邪�A���̖��x���̕ی����t����ׂ��҂̏��ʂƂ��āA���������͎̂��̂����ǂꂩ�B(15-2A�̗ތ^)
�@A�F�@�z��ҁA�q�A����A�c����A���A�Z��o��
�@B�F�@�q�A�z��ҁA����A�Z��o���A���A�c����
�@C�F�@�z��ҁA�q�A����A���A�c����A�Z��o��
�@D�F�@�q�A�z��ҁA����A�c����A�Z��o���A��
�@E�F�@�z��ҁA�q�A����A�c����A�Z��o���A�� |
|
��������� |
|
��
��
�l |
15
2D |
�@�ی����t���錠����L����҂����S�����ꍇ�ɂ����āA���S�����҂����S�O�ɂ��̕ی����t�𐿋����Ă��Ȃ������Ƃ��ɁA���Ȃ̖��ł��̕ی����t�𐿋����邱�Ƃ��ł���̂́A���S�����҂̑����l�ł���B(15-2A�̉��p) |
|
��������� |
|
15
2E |
�@���x���̕ی����t���錠����L����҂����S�����ꍇ�ɂ����āA���̎��S�����҂Ɏx�����ׂ����x���̕ی����t�ł܂����̎҂Ɏx�����Ȃ��������̂�����Ƃ��́A���̎҂̑����l���A���̖��x���̕ی����t�̐������҂ƂȂ�B(15-2D�̗ތ^) |
|
����������@ |
|
|
���x���̈⑰�⏞�N�� |
30
4� |
�@�J�Еی��@�Ɋ�Â��⑰�⏞�N�����錠����L����҂����S�����ꍇ�ɂ����āA���̎��S�����҂Ɏx�����ׂ��⑰�⏞�N���ł܂����̎҂Ɏx�����Ȃ��������̂�����Ƃ��́A���Y�⑰�⏞�N�����邱�Ƃ��ł��鑼�̈⑰�́A���Ȃ̖��ŁA���̖��x���̈⑰�⏞�N���̎x���𐿋����邱�Ƃ��ł���B(��b) |
|
����������@ |
|
30
4� |
�@�J�Еی��@�Ɋ�Â��⑰�⏞�N�����錠����L����҂����S�����ꍇ�ɂ����āA���̎��S�����҂����S�O�ɂ��̈⑰�⏞�N���𐿋����Ă��Ȃ������Ƃ��́A���Y�⑰�⏞�N�����邱�Ƃ��ł��鑼�̈⑰�́A���Ȃ̖��ŁA���̈⑰�⏞�N���𐿋����邱�Ƃ��ł���B(30-4�A�̗ތ^) |
|
����������@ |
|
���ꏇ�ʎ҂�����
�l |
15
2C |
�@���x���̕ی����t����ׂ������ʎ҂�2�l�ȏ゠��Ƃ��́A����1�l�����������́A�S���̂��߂��̑S�z�ɂ��Ă������̂Ƃ݂Ȃ���A����1�l�ɑ��Ă����x���́A�S���ɑ��Ă������̂Ƃ݂Ȃ����B(��b) |
|
��������� |
|
19
3D |
�@�ی����t���錠����L����҂����S�����ꍇ�ɂ����āA���̎��S�����҂Ɏx�����ׂ��ی����t�ł܂����̎҂Ɏx�����Ȃ��������̂�����ꍇ�ɂ����āA���̖��x���̕ی����t����ׂ������ʎ҂�2�l�ȏ゠��Ƃ��́A����1�l�����������́A�S���̂��߂��̑S�z�ɂ��������̂Ƃ݂Ȃ����B(15-2C�̗ތ^) |
|
��������� |
|
30
4� |
�@�J�Еی��@�Ɋ�Â��ی����t���錠����L����҂����S���A���̎҂����S�O�ɂ��̕ی����t�𐿋����Ă��Ȃ������ꍇ�A���x���̕ی����t����ׂ������ʎ҂�2�l�ȏ゠��Ƃ��́A����1�l�����������́A�S���̂��߂��̑S�z�ɂ��������̂Ƃ݂Ȃ���A����1�l�ɑ��Ă����x���́A�S���ɑ��Ă������̂Ƃ݂Ȃ����B(15-2C�̗ތ^) |
|
��������� |
|