「この法律は、労働組合法と相俟って、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もって経済の興隆に寄与することを目的とする」
「6条 この法律において労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態又は発生する恐れがある状態をいう」
「7条 この法律において争議行為とは、同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)、作業所閉鎖(ロックアウト)その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう」
2.2.届出(9条)
「争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事(船員に関しては地方運輸局長)に届け出なければならない」
1D
| 正しい | 誤り |
3.1 あっせん
「12条 労働争議が発生したときは、労働委員会の会長は、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基いて、斡旋員名簿に記されている者の中から、斡旋員を指名しなければならない」
「13条 あっせん員は、関係当事者間を斡旋し、双方の主張の要点を確め、事件が解決されるように努めなければならない」
3.2 調停
「18条 労働委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、調停を行う」
| 1 | 関係当事者双方から、調停の申請がなされたとき |
| 2 | 関係当事者の双方又は一方から、労働協約の定めに基づいて、調停の申請がなされたとき |
| 3 | 公益事業に関する事件につき、関係当事者の一方から、調停の申請がなされたとき、 又は、労働委員会が職権に基づいて、調停を行う必要があると決議したとき。 |
| 4 | 公益事業に関する事件、規模の大きい事件、若しくは特別の性質の事業に関するものであるために、公益に著しい障害を及ぼす事件につき、厚生労働大臣又は都道府県知事から、調停の請求がなされたとき |
「調停委員会は、調停案を作成して、これを関係当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、その調停案は理由を附してこれを公表することができる。この場合必要があるときは、新聞又はラジオによる協力を請求することができる」
3.3 仲裁
「30条 労働委員会は、次の各号の一に該当する場合に、仲裁を行う」
| 1 | 関係当事者の双方から、仲裁の申請がなされたとき |
| 2 | 関係当事者の双方又は一方から、労働協約の定めに基づいて、調停の申請がなされたとき |
仲裁委員会
「31条 法改正(H25.06.14) 労働委員会による労働争議の仲裁は、3人以上の奇数の仲裁委員をもつて組織される仲裁委員会を設け、これによつて行う」
「31条の4 仲裁委員会は、委員長が招集する」
「同2項 法改正(H25.06.14) 仲裁委員会は、仲裁委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない」
「同3項 仲裁委員会の議事は、仲裁委員の過半数でこれを決する」
「33条 仲裁裁定は、書面に作成してこれを行う。
その書面には効力発生の期日も記さなければならない」
「34条 仲裁裁定は、労働協約と同一の効力を有する」
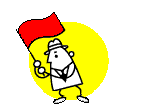 斡旋、調停を受け入れるか否かは自由。仲裁裁定は労働協約と同じ効力で双方に拘束力を持つ。
斡旋、調停を受け入れるか否かは自由。仲裁裁定は労働協約と同じ効力で双方に拘束力を持つ。
「31条 法改正(H25.06.14) 労働委員会による労働争議の仲裁は、3人以上の奇数の仲裁委員をもつて組織される仲裁委員会を設け、これによつて行う」
「31条の4 仲裁委員会は、委員長が招集する」
「同2項 法改正(H25.06.14) 仲裁委員会は、仲裁委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない」
「同3項 仲裁委員会の議事は、仲裁委員の過半数でこれを決する」
「33条 仲裁裁定は、書面に作成してこれを行う。
その書面には効力発生の期日も記さなければならない」
「34条 仲裁裁定は、労働協約と同一の効力を有する」
5D
| 正しい | 誤り |
4.1 緊急調整
「35条の2 内閣総理大臣は、事件が公益事業に関するものであるため、又はその規模が大きいため、若しくは特別の性質の事業に関するものであるために、争議行為により当該業務が停止されるときは国民経済の運行を著しく阻害し、又は国民の日常生活を著しく危くする恐れがあると認める事件について、その恐れが現実に存するときに限り、緊急調整の決定をすることができる」
「38条 緊急調整の決定をなした旨の公表があったときは、関係当事者は、公表の日から50日間は、争議行為をなすことができない」
4.2 争議行為の制限禁止等
「36条 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又はこれを妨げる行為は、争議行為としてでもこれをなすことはできない」
「37条 公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない」